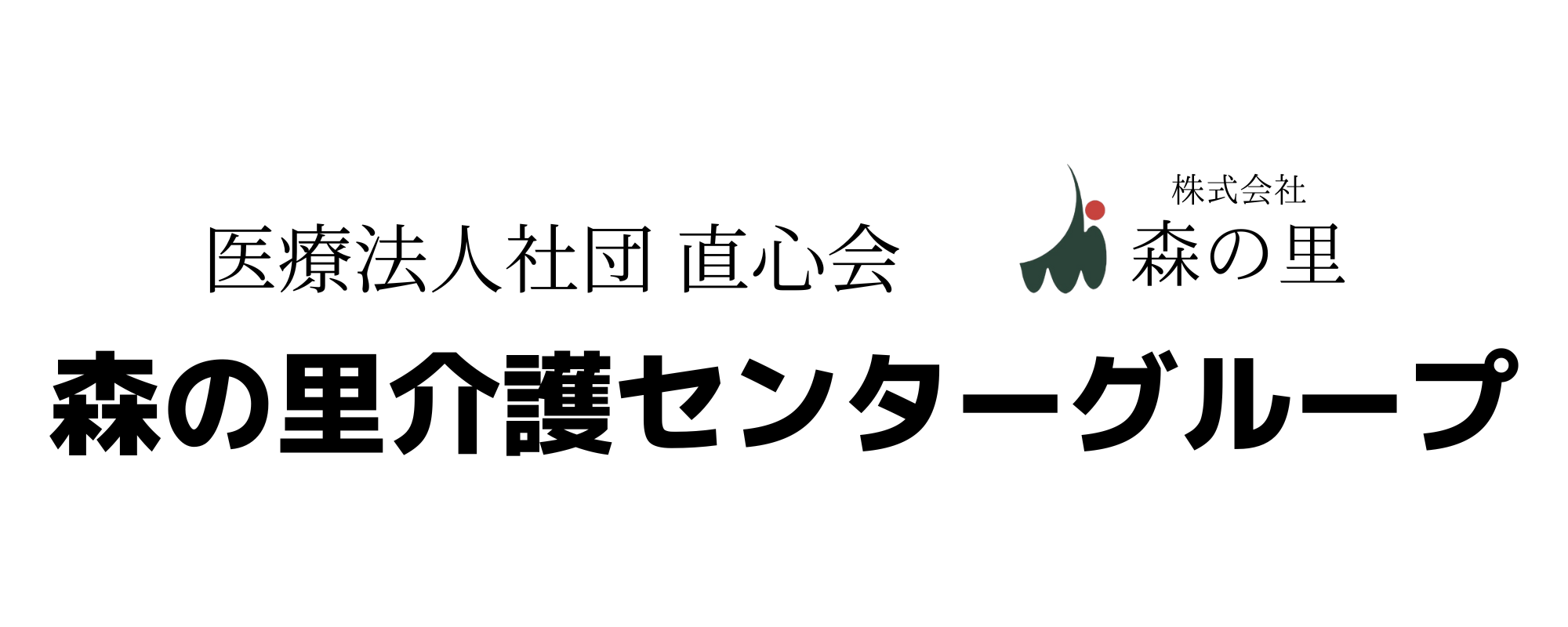【事務長ブログ】離設が教えてくれたこと|「役割」が人を支える力に

毎日が99キロと100キロをさまよい続けておりますw
理由はこれ↓

ジャンボママのエビチリレシピにハマりまくって食べちゃってます(汗)
で、本題(今日は早めw)
ここからは、めっちゃ真面目ですよ!
本当の介護ってこういうことなんだろうな?という出来事というか取り組み
今日は、現場の中で職員の方々が気づき、動いたある出来事について書いてみます。
先日、施設で同じ方による離設(無断での外出)が2回発生しました。
もちろん、見守り体制は取っていましたが、他の介助が重なるタイミングでは、どうしても一瞬の隙が生まれてしまいます。
残念ながらこうしたケースは、介護の現場では決して珍しいことではありません。
ご利用者様にとってはグループホームはご自宅なので、外出は良いんですよ。
でも、認知能力が低下した方の無断での外出は怪我や事故に直結してしまいます。
安全を厳守しないといけないという施設の立場上、物理的な対策として、鍵の管理や出入口の見直しなどはすぐに見直しました。
でもその一方で、もっと根本的な部分に目を向けてみよう!
と、職員の方々が相談し合い、真剣に考えてくれたんです。
「外に出たくなる背景には、ここにいる理由や意味が感じられないことがあるのかもしれない。」
「“やること”“役割”があれば、気持ちが変わるんじゃないか。」
そうして職員たちが出したアイデアが、
ご本人に家庭菜園をお願いしてみるというものでした。
さっそく小さな畑(プランター)を整え、ご本人に「水やりをお願いしていいですか?」と声をかけると、
「お、いいよ、もちろん。」と笑ってくださいました。

今では日課のように畑に足を運び(言うても敷地内ですが… というよりプランターですが)、スタッフや他の利用者さまとも会話が増え、自然な交流が生まれています。

離設という出来事は、決して軽く見てはいけないことですが、
それをきっかけに、職員の方々が“この方の生活に必要なもの”を見つめ直し、形にしてくれたことに感謝しています。
「守る」だけでなく、「活かす」「任せる」「つながる」。
介護において本当に大事なのは、そんな時間や関係性なのかもしれません。
これからも、現場で生まれる工夫や気づきを、こうして少しずつ伝えていけたらと思っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
森の里は今日も平和です。
おっと、最後に森の里事務長のYouTubeもよろしくお願いします。(チャンネル登録と高評価もね)